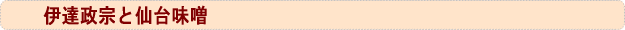 |
| |
四百年以上の歴史と伝統を持つ「仙台味噌」は、関西の白味噌に対して、赤味噌の代表格として、安土・桃山時代(1573年頃から1603年)から全国的にその名を知られていました。
16世紀後半、日本全国を統治していた豊臣秀吉公は、朝鮮へ勢力をのばそうと、各藩の大名に出兵を命じます。兵は兵糧(ひょうろう)である各自の地元の味噌を携えて朝鮮へ出発。
長い滞陣の間に、他藩の味噌は変質してしまいましたが、仙台藩祖・伊達政宗公が持参していた味噌は唯一変質しなかったため、「仙台味噌は質が良い」と評判になりました。そして、この評価は全国的に高まっていったのです。 |
| |
江戸市中には七ヶ所の仙台藩邸があり、そこに住む三千人の侍に分け与える為、江戸でも味噌を造る事となります。原料の大豆と米は海路を用い仙台よりすべて運ぶ程の徹底ぶり。
その評判すこぶる良く2代目藩主忠宗の頃から一般にも払い下げられ、江戸市民にも伊達家の味噌の良さが広がり、江戸市民の手によって「仙台味噌」の名が付けられました。
政宗は仙台城築城後,中に敷地900坪という「御塩噌蔵」(ごえんそぐら)という味噌蔵を設けます。そこで常州(常陸の国)から招いた真壁市兵衛を中心に醸造を始め、やがて14名の町方味噌屋と
「味噌仲間」が結成される事となります。 |
| |
 |
佐々重も味噌仲間へ加入
佐々重は天保5年(1834年)この「味噌仲間」に
加入し、安政元年(1854年)10月に味噌の販売を
始めました。
当時は大変な飢饉や大地震もあり3度の失敗を経て、4年目にして味噌が出来上がったと記録に残っております。
残念ながら当時の資料は、太平洋戦争の仙台空襲で殆ど消失してしまいました。 |
|
| |
| |
| 全国の味噌からみた仙台味噌 |
原料による
分類 |
味、色分類 |
塩分% |
麹歩合 |
麹原料 |
醸造期間 |
主な銘柄 |
椀当味噌量 |
| 米味噌 |
甘味噌 |
白 |
5~7 |
15~30 |
米 |
5~20日 |
西京味噌 |
30.0~21.4g |
| 赤 |
5~7 |
12~20 |
米 |
5~20日 |
江戸甘味噌 |
30.0~21.4g |
| 甘口味噌 |
淡色 |
7~12 |
8~15 |
米 |
5~20日 |
柏白味噌 |
21.4~12.5g |
| 赤 |
11~13 |
10~15 |
米 |
3~6ヶ月 |
中味噌 |
13.6~11.5g |
| 辛口味噌 |
淡色 |
11~12 |
5~10 |
米 |
2~3ヶ月 |
信州味噌 |
13.6~12.5g |
| 赤 |
11~13 |
5~10 |
米 |
3~12ヶ月 |
仙台味噌
越後味噌 |
13.6~11.5g |
| 麦味噌 |
甘口味噌 |
淡色 |
9~11 |
15~25 |
麦 |
1~3ヶ月 |
長崎味噌
薩摩味噌 |
16.7~13.6g |
| 辛口味噌 |
赤 |
11~13 |
8~115 |
麦 |
3~12ヶ月 |
大分味噌 |
13.6~11.5g |
| 豆味噌 |
辛 |
10~12 |
全量 |
大豆 |
5~12ヶ月 |
八丁味噌 |
15.0~12.5g |
|
| ※麹歩合は麹用の米または麦の重量÷大豆の重量×10であらわします。 |
| |
▼仙台味噌の特徴
仙台味噌は米麹を使った米味噌の辛口、赤味噌です。
麹(こうじ)が増えると甘味間が増し、大豆が増えると旨味が増えます。また熟成期間を長く取ることで発酵が進み米から生まれた甘味を酵母がアルコールを作り、これが味噌の良い香りとなります。
▼昆布文化から京都の白味噌を見てみましょう
昔、北海道で収穫された昆布は波の穏かな日本海側を下り、琵琶湖の周りを陸送し京都に入ります。
また鰹節の文化との出会いから京料理が確率していくのですが、この出汁文化は京都の味噌文化にも変化をもたらし、味噌に甘味を求めるもとなっていきます。
つまり、旨味は出し汁から、甘味は味噌からという具合です。
|
| |
▼出し汁文化のない仙台
一方、仙台には昆布の文化はありませんでした。
しかし、仙台平野に恵まれたこの地は、海の幸、山の幸が豊富でその素材をいかす調味料が必要でした。
それが熟成のきいた仙台味噌だったのです。味噌の熟成期間が長いことで少量でも味が伸び、素材の良さを100%引き立てる味噌となっております。味噌汁に仕立てますと、素材の違いにより味噌汁の味が異なり毎日食べても飽きのこない味噌汁を楽しむことが出来ます。
特にお奨めの具はアサリとシジミで、飲んでいるとすーっと気持ちが落ちついてきます。
他には個性の強い素材、例えば、豚汁、サバの味噌煮、牡蠣鍋、ウドの味噌サラダなどにも相性が良くお奨めです。 |
| |
| |
| |
 佐々重のトップページへ戻る 佐々重のトップページへ戻る |
| |